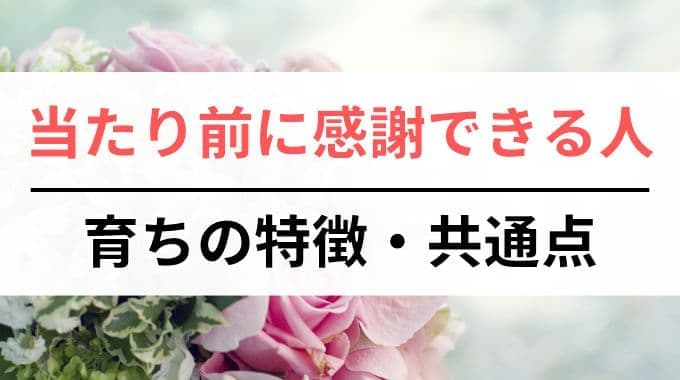「ありがとう」って、自然に言える人と、なかなか言えない人がいますよね。
ちょっとした一言なのに、意外と難しい。
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、感謝が自然に出る人には、共通する育ち方や心理の特徴があります。
この記事では、「当たり前に感謝できる人」がどんな家庭で育ち、どんな価値観を持っているのかを紹介します。
今の自分を変えたい人にも、ヒントになるはずです。
当たり前に感謝できる人の「育ち」に共通する家庭環境

感謝が自然にできる人の多くには、ある共通した家庭の雰囲気や、親との関わり方があります。
ここでは、そんな“感謝の心”が育ちやすい家庭環境の特徴について紹介していきます。
親が感謝を“言葉にする”習慣を持っていた
親が日常的に「ありがとう」と口にしていた家庭では、子どもも自然とその大切さを感じ取ります。
たとえば、
ごはんを作ってくれた→「美味しかったよ、ありがとう」
何かしてもらったとき→「助かった!」
など、感謝の言葉を伝える。
こういう日常の小さな言葉のやりとりが、子どもの中にも「感謝を言葉で伝えるのは当たり前」という感覚を育てます。
親の背中を見て育った子どもは、無理に教えなくても「ありがとう」が自然に言えるようになるのです。
小さなことを大切にする価値観があった
感謝の心は、特別なときだけ必要なものではありません。
日々のちょっとしたことにも「ありがたいな」と思える感性が大切です。
たとえば、
「今日は天気がよくて気持ちいいね」
「だれかが手伝ってくれて助かったね」
といった、小さなことにも目を向ける家庭では、自然と“感謝する心”が育ちます。
こうした価値観の中で育つと、子どもは人のやさしさや思いやりに気づきやすくなり、感謝の気持ちを当たり前に持てるようになります。
「してもらって当然」ではない家庭の空気
家族の中でも、「やってもらうのが当たり前」といった空気がない家庭では、感謝の気持ちが育ちやすいです。
たとえば、洗濯や料理など、誰かがしてくれることに対して「ありがとう」と言う習慣がある場合。
子どももそれを見て、
「人のしてくれることは当たり前じゃない」
と感じるようになります。
そうした家庭では、何かしてもらったときに、素直に「ありがとう」が出てくるんです。
「ありがとうを強制しない」自由な空気
感謝の言葉って、強制されると気持ちがこもらなくなりますよね。
たとえば、
「ちゃんとありがとう言いなさい」
と言われて無理に言うよりも、親が自然と、
「ありがとう」
と、口にしている姿を見ることで、子どもは自分のタイミングでその大切さに気づいていきます。
無理に言わせるのではなく、「ありがとうを言いたくなる空気」があること。
それが、心からの感謝を育てるポイントなんです。
当たり前に感謝できる人の内面にある心理的特徴
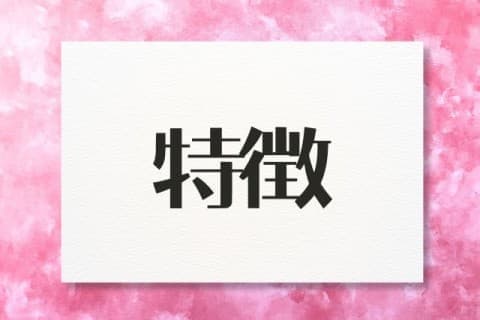
ここでは、感謝が日常的にできる人の“心の中”にある共通する考え方や心理的な特徴を紹介していきます。
他人との比較が少なく、自分軸で物事を見る
感謝できる人は、他人と自分をあまり比べません。
たとえば、
- 「あの人の方が得してる」
- 「自分は損してばかり」
などと感じることが少ないため、自然と心が穏やかで、自分の環境や周囲の人への感謝に目を向ける余裕があります。
逆に、常に人と比べてばかりだと、自分の足りないところばかりが気になってしまい、「感謝よりも不満」が出てきやすくなります。
自分軸で物ごとを見るというのは、「今の自分にとってこれはありがたいことだ」と感じる力。
感謝は、周りと比べないことで見えてくるものでもあるんです。
欠乏感よりも“充足感”をベースにしている
感謝できる人は、いつも「何かが足りない」と感じているわけではありません。
むしろ「すでにあるもの」に目を向けることができています。
たとえば、
「忙しいけどごはんが食べられてありがたい」
「大変だけど、支えてくれる人がいるのは心強い」
など、小さな満足や喜びをちゃんと感じ取れる人です。
心のベースに“充足感”があると、不思議と感謝の気持ちも自然に湧いてくるもの。
「もっと、もっと」と思い続けるのではなく、
「今あるものって、けっこうありがたいよね」
と感じることが、感謝を育てる土台になります。
感謝を「損」だと感じていない
感謝の気持ちを表すのって、時に“ちょっと恥ずかしい”と感じる人もいます。
あるいは、「お礼を言ったら相手の立場が上になってしまう」なんて、無意識に思っていることも。
でも、感謝できる人は、そういう損得をあまり気にしていません。
「ありがとう」は、自分の心の豊かさを表すものだと知っているからです。
むしろ、自分から「ありがとう」を伝えることで、相手との関係がよくなることも知っています。
感謝をすることは、損どころか、人間関係を育てる“投資”のようなもの。
そんなふうに自然ととらえているのが、感謝できる人の心理的な特徴です。
当たり前に感謝できない人の育ちの傾向

ここでは、感謝の気持ちを持ちにくくなる背景について、よくある育ちのパターンを紹介していきます。
感謝を強制されてきた経験がある
「ちゃんとありがとう言いなさい!」
子どものころ、こんなふうに言われて嫌な気持ちになったことがある人もいるかもしれません。
感謝の言葉を“しつけ”として厳しく教えられた場合、「ありがとう=言わされるもの」という印象が残ってしまうことがあります。
その結果、大人になっても、
「感謝は義務」
「素直に言うのがなんだか嫌」
という気持ちを引きずってしまうことも。
本来、感謝って“感じたときに自然に出るもの”ですよね。
でも、それを無理やり言わされる環境にいた人にとっては、感謝そのものが少し苦い記憶と結びついてしまうことがあるんです。
家族間であまり感謝の言葉が交わされなかった
「ありがとう」って、親から言われた記憶がない。
そんな家庭で育った人は、感謝の言葉を使う機会そのものが少なくなりがちです。
特に家族の間で、
- 「やってもらうのが当たり前」
- 「親は子に尽くすのが当然」
とされていたりすると、感謝のやりとりが少ないまま育つこともあります。
子どもは、大人が日常で使っている言葉をまねしながら育ちます。
だから、感謝の言葉がほとんど交わされていない家庭では、「ありがとう」を使う習慣そのものが身につきにくいんです。
頼ること=悪いことという価値観
感謝って、自分ひとりではできないことを誰かにしてもらったときに自然と生まれるもの。
でも、育ってきた中で、
- 「人に頼るのは迷惑」
- 「自分のことは自分でやるべき」
という価値観が強く刷り込まれていると、そもそも誰かの助けを受け入れにくくなります。
そして、誰かに頼らない=誰かに感謝する場面が少ない、ということにもつながります。
「甘えてると思われたくない」
そんな気持ちが強い人は、助けられても「感謝する」より「申し訳ない」と感じてしまうこともあるのです。
感謝が自然にできるようになるための3つのヒント

「ありがとう」をもっと自然に言えるようになりたい。
そう思っても、いきなり感謝体質になるのはちょっと難しく感じることもありますよね。
でも、少し意識するだけで、日々の中に感謝の気持ちを見つけることは十分できます。
ここでは、感謝を習慣にしていくための、ちょっとしたコツを3つご紹介します。
感謝日記をつける
まずおすすめなのが、その日に感謝できたことを日記に書き出してみることです。
- 「今日は天気が良くて気持ちよかった」
- 「友達が声をかけてくれた」
- 「おいしいコーヒーを飲めた」
など、どんな小さなことでもOK。
最初は1日1つでも十分です。
書き続けていくうちに、日常のなかで「ありがたい」と感じる感度がどんどん高まっていきます。
ポイントは、「すごいこと」じゃなくて「なんとなく、ありがたかったな」で大丈夫なこと。
感謝のタネは、意外とすぐそばにたくさん転がっているんです。
身近な人に“意識して”ありがとうを伝える習慣
照れくさくて、つい言いそびれてしまう「ありがとう」。
でも、それをちょっと意識して口に出すだけで、自分も相手も気持ちが明るくなります。
たとえば、家族がご飯を作ってくれたとき、同僚がちょっとした気遣いをしてくれたとき。
「ありがとう」を声に出すことで、自分の中にも“感謝する気持ち”がしっかり根づいていきます。
ポイントは、“意識して”やること。
慣れてくると、だんだん自然に出るようになってきますよ。
自分自身に対しても「ありがとう」を言ってみる
感謝の対象は、人だけじゃありません。
自分自身にも「ありがとう」と伝えてみるのも、とても大事な習慣です。
「今日はちゃんと起きられてえらい」
「疲れてたのにがんばった、自分ありがとう」
そんなふうに、自分のがんばりや存在に対して、あたたかい言葉をかけてあげてください。
自分を大切にできる人は、自然と他人にもやさしくなれます。
そして、自分への感謝が増えると、日々の中にある「ありがたいこと」にも敏感になっていきます。
まとめ
今回は、当たり前に感謝できる人の育ちの特徴や共通点などについてご紹介しました。
感謝できる人には、家庭環境や心の持ち方に共通点があります。
ただ、それは“特別な人”だけのものではなく、日常の中で少しずつ育てていけるものです。
親しい人に「ありがとう」を伝える、自分のがんばりを認めてあげる。
そんな小さな行動の積み重ねが、感謝を自然に感じられる心を育ててくれます。
大切なのは、「気づこうとすること」と「伝えようとすること」。
その意識が、感謝にあふれたあたたかい毎日につながっていきます。