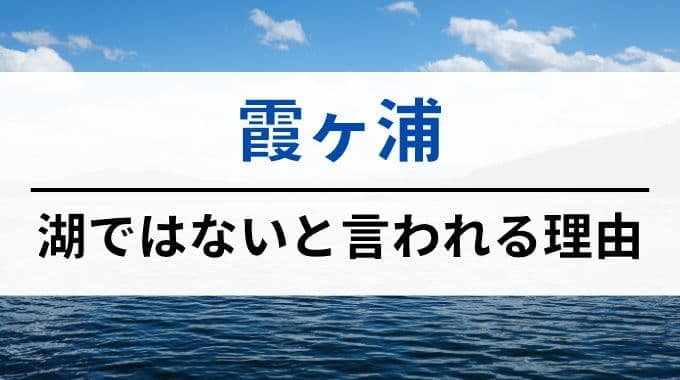「霞ヶ浦って湖じゃないの?」
このように思ったことはありませんか?
実は、霞ヶ浦は一般的な湖とはちょっと違う特徴を持っているんです。
そのため、「湖ではない」と言われることも…。
この記事では、霞ヶ浦が「湖ではない」と言われる理由を分かりやすく解説していきます。
霞ヶ浦が「湖ではない」と言われる理由
一般的に、湖の名前には最後に「湖」という字がつくことが多いですよね。
しかし、「霞ヶ浦」にはその「湖」の字がありません。
実は、これにはちゃんとした理由があるのです。
「浦」という言葉には、
- 陸地に広がる海や湖の入り組んだ部分
- 海辺
を意味するという特徴があります。
つまり、「霞ヶ浦」は、もともと海の一部だったことから、「湖」ではなく「浦」という名前になったのです。
日本国内で2番目に広大な湖とされている霞ヶ浦ですが、実はもともと海とつながっていました。
長い年月をかけて自然の力や人の手によって形が変化。
結果、現在の霞ヶ浦が形成されたため、「霞ヶ浦は湖ではない」と言われることもあるのです。
また、『常陸風土記』には、
霞ヶ浦にはクジラ以外のあらゆる魚が生息していた
と記されていたそうで、当時は「流れ海」と呼ばれていたとも伝えられています。
8世紀に編纂された「常陸(ひたち)風土記」という書物には、クジラ以外ならどんな魚でもいたとか、ハマグリが獲れたとか、藻を焼いて塩をつくっていたと書かれています。名前も「流れ海」と呼ばれていました。
実際に霞ヶ浦には多くの河川が流れ込んでおり、かつては満潮時に海水が逆流することもあったそうです。
そのため、まるで流れのある海のような景色が広がっていたと考えられています。
このような特徴から、「流れ海」と呼ばれるようになったのかもしれません。
霞ヶ浦は、かつては陸地に深く入り込んだ内湾のような地形をしていました。
そこへ多くの河川が流れ込み、河川が運んできた土砂が湾の入り口に堆積することで、徐々に海水の流入量が減少していきました。
その結果、霞ヶ浦は海水と淡水が混ざる「汽水湖」へと変化し、現在の形になったのです。
霞ヶ浦はかつて海だった?
今から1000年以上前の8世紀頃。
霞ヶ浦一帯は、現在の利根川下流域に広がっていた「香取海」の入り江のひとつで、「香澄流海」と呼ばれていたとされています。
当時の霞ヶ浦は、現在の2~3倍もの広さを誇り、海水が自由に出入りできる大きな湖だったとされています。
しかし、その後、
- 利根川
- 鬼怒川
- 小貝川
といった河川が運んできた土砂が少しずつ湾の入口に堆積し、現在の霞ヶ浦の形へと変化していきました。
現在の「西浦」や「北浦」も、この堆積によって生まれたものと考えられています。
そもそも、かつての関東平野一帯は「古東京湾」と呼ばれ、浅い海の底に広がっていたとされています。
その当時、地球の気候は激しく変動しており、氷期と間氷期が何度も繰り返されていました。
氷期になると海面が大きく下がり、関東平野は陸地として姿を現しました。
一方、間氷期になると海面が上昇し、再び海に沈むというサイクルが続いていたようです。
氷期に陸地化した際には、雨風によって地表が削られ、川が山から土砂を運んできては徐々に積み重なっていきました。。
また、間氷期に再び海に沈むと、海底には泥や砂が蓄積されていったのです。
このように、気候変動が繰り返されるなかで土砂が蓄積し、長い年月をかけて現在の霞ヶ浦の姿が形作られていったと考えられています。
まとめ
今回は、霞ヶ浦が「湖ではない」と言われる理由を中心にご紹介しました。
霞ヶ浦は、もともと海の一部であり、「湖」とは異なる特徴を持つことから「湖ではない」と言われることがあります。
そして、かつては「香澄流海」と呼ばれ、現在の2~3倍の広さを誇っていました。
しかし、河川が運んできた土砂の堆積によって形が変わり、現在の霞ヶ浦へと変化していったのです。